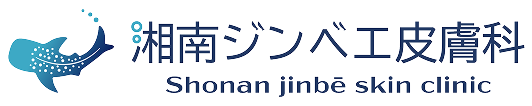伝染性膿痂疹(とびひ)
夏場になると、子どもの肌に小さな水ぶくれや赤いブツブツが出て、かゆみを訴えることがあります。もしかするとそれは「とびひ」の症状かもしれません。正式には「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」といい、細菌によって起こる皮膚の感染症です。見た目は軽そうでも感染力がとても強いため、早めの対応が大切です。
このページでは、とびひの原因や種類、うつる仕組み、家庭でのケアなど、わかりやすく解説していきます。
とびひ(伝染性膿痂疹)とは
とびひは、主に「黄色ブドウ球菌(おうしょくブドウきゅうきん)」や「溶連菌(ようれんきん)」といった細菌が、皮膚に入り込んで感染を引き起こす病気です。虫刺されや引っかき傷、アトピーなど、皮膚のバリアが弱っているところから菌が侵入し、赤み・水ぶくれ・カサブタなどの症状が現れます。強いかゆみを伴うことも多く、かいたせいで他の部位にもどんどん広がっていくのが特徴です。
とびひは特に子どもに多く見られますが、大人でも免疫が落ちているときは感染することがあります。感染力が非常に強いため、家族や園・学校などで広がってしまうこともあります。
とびひの種類
とびひには、大きく分けて2つのタイプがあります。
①水疱性膿痂疹(すいほうせいのうかしん)
黄色ブドウ球菌が出す毒素が原因で起こります。薄い膜のような水ぶくれができ、それが破れてジクジクとしたただれ(びらん)になります。比較的軽症で、全身症状は出にくいのが特徴です。しかし、小さなお子様で全身の皮膚に症状が広がった場合や、強い炎症がある場合、発熱やリンパ節の腫脹、咽頭痛などの症状がみられることもあります。
※まれに、黄色ブドウ球菌が出す毒素が全身に広がると「熱傷様皮膚症候群(ねっしょうせいひふしょうこうぐん)」という重症の皮膚疾患を起こすことがあります。皮膚が広範囲にめくれ、発熱を伴うこともあるため注意が必要です。
②痂皮性膿痂疹(かひせいのうかしん)
溶連菌や黄色ブドウ球菌によって起こります。水疱はできにくいですが、皮膚が赤く腫れて分厚いカサブタ(痂皮:かひ)を作ります。発熱やリンパ節の腫脹、咽頭痛などの症状がみられることもあります。
感染経路
とびひは、接触によって感染が広がっていきます。
・患部に直接触れる(兄弟や友達同士の接触など)
・タオルや衣類、おもちゃを共有する(間接的な接触)
・自分でかいた手で別の場所を触って広がる(自己感染)
また、アトピー性皮膚炎などで皮膚が乾燥しやすく、かゆみがある方は特に感染しやすい傾向があります。皮膚のバリアが低下している状態にあるためです。ただし健康な皮膚の方でも、小さな傷ができてしまうことはよくある話です。つまり、とびひは誰にでも起こりうる身近な皮膚トラブルです。うつさない・うつらないためにも、早めの治療と正しいケアが大切です。
治療法
とびひの治療には、主に抗生物質が用いられます。皮膚の状態や症状の程度によって、塗り薬(抗菌薬の軟膏)や飲み薬(内服薬)を使い分けます。治療が効いてくれば、通常は1〜2週間ほどで治ります。ただし、症状が軽くなったからといって自己判断で薬をやめてしまうと、再発や悪化のリスクがあるため、最後までしっかり治療を続けましょう。
治療中の注意点
・患部を清潔に保つ:石けんをよく泡立てて、シャワーでやさしく洗ってください。ゴシゴシこすらず、泡でなでるように洗うのがポイントです。洗い終わった後は清潔なタオルで軽く水分を拭き取ります。
・薬は正しく使う:軟膏を塗る前後は、手を洗いましょう。患部に薄く均一に塗り広げ、必要があれば清潔なガーゼや包帯で覆います。外用薬も内服薬も、決められた用法・用量を守ってお使いください。
・爪は短く切る:とびひは、かきむしってしまうと感染が広がりやすくなります。爪を短く切ると、無意識に掻いてしまっても皮膚へのダメージが軽減する上、爪の間を清潔に保ちやすくなります。
・身の回りのものを清潔に:タオル、寝具、衣類などは家族と共有せず、こまめに洗濯しましょう。
・お風呂の注意点:一人ずつ順番に入り、湯船は避けてシャワーで済ませるのが安心です。
まとめ
とびひ(伝染性膿痂疹)は、細菌感染によって起こる皮膚の病気です。子どもに多く、かゆみを伴う水ぶくれやカサブタが特徴です。感染力が強いため、早期の診断と治療、正しいケアが大切です。少しでもおかしいと感じた場合は、皮膚科などの医療機関へご相談くださいね。
参考文献一覧
・Dollani LC, Marathe KS. Impetigo/Staphylococcal Scalded Skin Disease. Pediatrics in Review. 2020;41(4):210–212.
・Brazel M, Desai A, Are A, Motaparthi K. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome and Bullous Impetigo. Medicina (Kaunas, Lithuania). 2021;57(11).

新聞や雑誌でのコラム執筆経験もあり、「塗るを楽しく」を合言葉にした絵本も製作中です。
よくあるご質問
- とびひは自然に治りますか?
- 自然に治ることもあります。しかし病状が悪化するリスクもあるため、自己判断で様子見することはオススメしません。早めに医師の診察を受け、適切な治療を受けましょう。
- とびひは夏だけに起きる病気ですか?
- とびひは夏に多いとされています。高温・多湿によって細菌が繁殖しやすいのが一因です。ただし夏以外の季節はとびひにならないわけではありません。